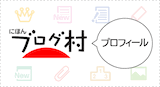分福茶釜の茂林寺
近くに行きたい場所があったので、分福茶釜の茂林寺に、お参りしてから行くことにしました。
分福茶釜の茂林寺

気づかなかったのですが、この辺には湿原があるのです。

茂林寺への参道は お土産屋さんが 沢山あります。

お店の看板の上にもタヌキさんが。
谷中銀座の猫ちゃんみたいですね。
んっ?どちらが先に 屋根に置き始めたのでしょうか。。。
どちらでもいいですね。

階段が3段ですし、スロープもあって、足が不自由でも行けそうです。

分福茶釜のお話が書いてあります。

両側に沢山のタヌキがいて、出迎えてくれます。

さらに左奥に 大きなタヌキさんが。

この日は 法事をしてました。

右側に、「この奥は有料です」とあります。
何か、展示してあるようです。
あまり時間がないので、スルーします

屋根が 綺麗に整えられたかやぶき屋根で 趣があります。
お手入れ大変でしょうね。

タヌキでないかたも いらっしゃいます。

早春には 白梅が美しく咲きます。
茂林寺の釜のお話
応永年間のこと。
上州(現・群馬県)の茂林寺という寺に守鶴という優秀な僧がいた。
彼の愛用している茶釜はいくら汲んでも湯が尽きないという不思議な釜で、僧侶の集まりがあるときはこの釜で茶を振舞っていた。
あるときに守鶴が昼寝をしている様子を別の僧が覗くと、なんと守鶴の股から狸の尾が生えていた。
守鶴の正体は狸、それも数千年を生きた狸であり、かつてインドで釈迦の説法を受け、中国を渡って日本へ来たのであった。
不思議な茶釜も狸の術によるものであったのだ。
正体を知られた守鶴は寺を去ることを決意した。
最後の別れの日、守鶴は幻術によって源平合戦の屋島の戦いや釈迦の入滅を人々に見せたという。
この説話をもとにして、昔話の『分福茶釜』が創作されたといわれている。
狸が 茶釜に化ける昔話は、有名ですね。
人間に恩があって茶釜に化け、お寺の和尚さんに正体が発覚する、という内容のお話です。
最後に
茂林寺が 本当にあるお寺というのは、知りませんでした。
![]() (*^_^*)ここまで読んでいただきまして、ありがとうございます。
(*^_^*)ここまで読んでいただきまして、ありがとうございます。